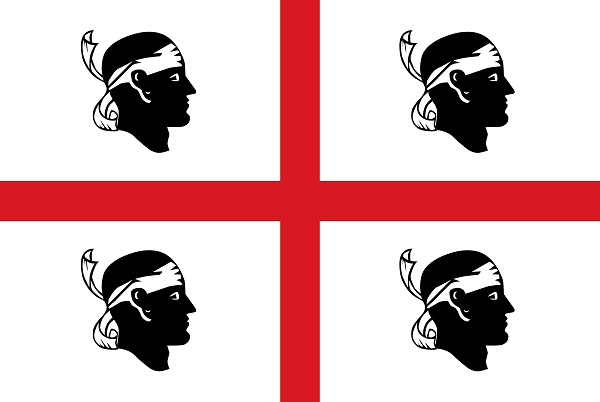いま英国議会下院で起きているBrexit(英国のEU離脱)をめぐる議論の嵐は、民主主義の雄偉を証明しようとする壮大な実験です。それが民主主義体制の先導国である英国で起きているからです。
そこでは民主主義の最大特徴である多数決(国民投票)を多数決(議会)が否定あるいは疑問視して、煩悶し戸惑い恐れ混乱する状況が続いています。それでも、そしてまさに民主主義ゆえに、直面する難題を克服して前進しようとする強い意志もまた働いています。
民主主義とは、民主主義の不完全性を認めつつ、より良いあり方を求めて呻吟することを厭わない政治体制のこと。だから議論を戦わせて飽くことがありません。言葉を変えれば、不都合や危険や混乱等々を真正面から見つめ、これに挑み、自らを改革・改善しようと「執拗に努力する」仕組みのことです。
民主主義は完全無欠なベスト(最善)の政体ではありません。他の全ての政治システムよりもベター(より良い)なだけです。しかしベストが存在しない限り、“ ベターがベスト ”です。チャーチルはそのことを指して、民主主義はそれ以外の全ての政治体制を除けば最悪の政治だ、と喝破しました。
2016年、英国議会はBrexitの是非を決められず、結果として市民の要請に応える形で国民投票を行いました。国民の代表であるはずの議会が離脱の当否を決定できなかったのはそれ自体が既に敗北です。しかし国民投票を誘導した時の首相ディヴィッド・キャメロンと議会はそのことに気づきませんでした。
国民投票の結果、Brexitイエスの結果が出ました。民主主義の正当な手法によって決定された事案はすぐに実行に移されるべきでした。事実、実行しようとして議会は次の手続きに入りました。そこでEUとの話し合いが進められ、責任者のメイ首相は相手との離脱合意に達しました。
ところが英国議会はメイ首相とEUの離脱合意の中身を不満としてこれを批准せず、そこから議会の混乱が始まりました。それはひと言でいえば、メイ首相の無能が招いた結果だったのですが、同時にそれは英国民主主義の偉大と限界の証明でもありました。
議会とメイ首相が反目し停滞し混乱する中、彼女はもう一方の巨大な民主主義勢力・EUとの駆け引きにも挑み続けました。そこではBrexitの是非を問う国民投票が、英国民の十分な理解がないまま離脱派によって巧妙に誘導されたもので無効であり、再度の国民投票がなされるべき、という意見が一貫してくすぶり続けていました。
だが改めての国民投票は、民主主義によって選択された国民の意志を、同じ国民が民主主義によって否定することを意味します。それは矛盾であり大いなる誤謬です。再度の国民投票は従って、まさに民主主義の鉄則によって否定されなければなりません。
そこで「議会で解決の道が探られるべき」という至極当たり前の考え方から論戦が展開されました。審議が続き採決がなされ、それが否定され、さらなる主張と論駁と激論が交わされました。結果、事態はいよいよ紛糾し混乱してドロ沼化している、というのが今の英国の状況です。
そうこうしているうちに時限が来て、EUは英国メイ首相の離脱延期要請を受け入れました。それでも、いやそれだからこそ、英国議会は今後も喧々諤々の論戦を続けるでしょう。それはそれで構わない。構わないどころか民主主義体制ではそうあるべきです。
だが民主主義に則った議会での議論が尽くされた感もある今、ふたたび民主主義の名において、何かの打開策が考案されて然るべき、というふうにも筆者には見えます。その最大最良の案が再度の国民投票ではないか、とも思うのです。
なぜ否定されている「再国民投票案」なのかといいますと、2016年の国民投票は既に“死に体”になっている、とも考えられるからです。民意は移ろい世論は変遷します。その変化は国民が学習することによって起きる紆余曲折であり、且つ進歩です。
つまり再度の国民投票は「2度目」の国民投票ではなく、新しい知識と意見を得た国民による「新たな」国民投票なのです。初の審判から経過3年、という月日が十分に長いかどうかは別にして、2016年の国民投票以降の英国の激動は、民主主義大国の成熟した民意が、民主主義の改善と進展を学ぶのに十二分以上の影響を及ぼした、と考えることもできます。
いうまでもなく英国議会は、メイ首相を信任あるいは排除する動きを含めてBrexitの行方を自在に操る権限を持っています。同時にこれまでのいきさつから見て、同議会はさらなる混乱と停滞と無力を露呈する可能性もまた高い。ならば新たな国民投票の是非も議論されなければならないのではないか、と考えます。
そうなった暁には、投票率にも十分に目が向けられなければなりません。そこでは前回の72,1%を上回る投票率があるほうが望ましい。2016年の国民投票後の分析では、EU残留派の若者が投票しなかったことが、離脱派勝利の大きな一因とされました。
もしもその分析が正しいならば、投票率の増加は若者層の意思表示が増えたことを意味し、同時にその結果がもたらす意味を熟知する離脱派の「熟年国民」の投票率もまた伸びて、2016年次よりもなお一層多くの国民が意思決定をした、と見なすことができるでしょう。
要するにBrexitをめぐる英国の混乱と殷賑は、既述したように民主主義の限界と悪と欺瞞と、同時にその良さと善と可能性を提示する大いなる実験なのです。それは民主主義の改革と前進に資する坩堝(るつぼ)なのであって、決してネガティブなだけの動乱ではありません。
動乱を「EU内の紛糾」と視野を広げ俯瞰して見た場合、大きな変革の波は、先ず英国と欧州の成熟した民主主義の上に、Brexit国民投票を実施した当人のデイヴィッド・キャメロン前首相という負け馬がいて、それにイタリアの負け馬マッテオ・レンツィ前首相が続き、テリーザ・メイ英国首相というあらたな負け馬が総仕上げを行っている、という構図です。
民主主義の捨て石となっている彼ら「負け馬」たちに、筆者はカンパイ!とエールを送りたい気持ちです。なぜなら3人は、民主主義の捨て石であると同時に、疑いなくそれのマイルストーンともなる重要な役割を果たしていて、民主主義そのものに大きく貢献している、と考えるからです。
facebook:masanorinakasone
official site:なかそね則のイタリア通信