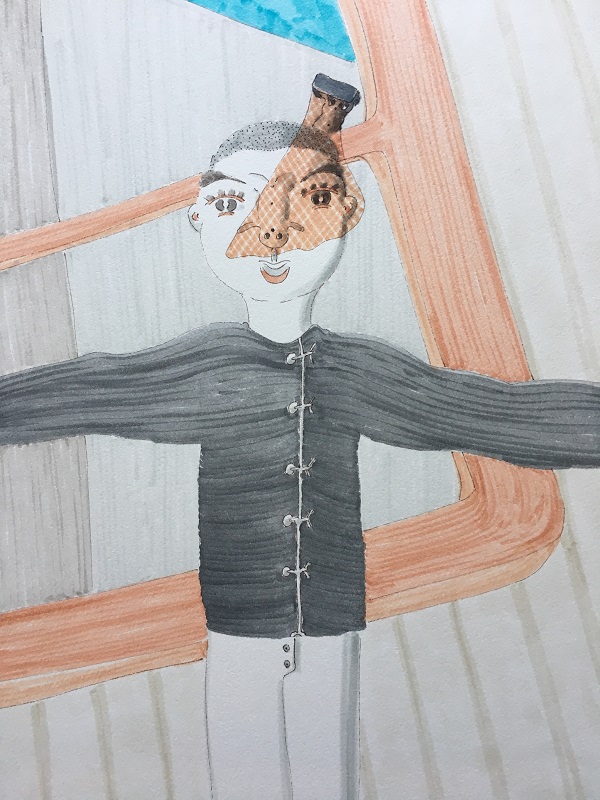イラスト:© ザ・プランクス
プロローグ
鼓俊一は妻の典子が肺がんで亡くなったとき、SNS上の友人とのやり取りを介してはじめて自分の喫煙が妻の死の遠因かもしれないと気づいた。
典子はほぼ1年前、腺がんのステージ4と診断された。肺がんの一種である腺がんは、女性や非喫煙者が罹る病気とされる。
本人にも夫の鼓にとっても寝耳に水のできごとだった。がんという病気自体もそうだが、末期のステージ4という診断がにわかには信じられなかった。だがそれはまぎれもない現実で、発見が引き金になったのでもあるかのように妻は強い痛みを訴えはじめた。幸い緩和ケアが行き届いた病院での治療だったため、典子は短い苦悶の時間をすごしただけで旅立った。
発見から死までの間、鼓は驚きと失意と無力感の底で、妻の看護に明け暮れた。体の多忙と気鬱の巨大のせいだったのか、鼓は妻の肺がんと自らの大量の喫煙を結びつけて考えることはなかった。
喫煙による健康への悪影響がうるさく言われだした1980年代まで、鼓は会社でも家でもどこでも、大量の煙草をすい続けた。だがところかまわずに喫煙するその習慣はほぼ40年前に終わった。鼓はそのころに禁煙宣言をした。しかしそれは表向きで、かれはひそかに喫煙を続けた。そうはいうものの禁煙宣言をした手前もあり、以来かれは家の中ではいっさい煙草をすわなくなった。
妻の受動喫煙についてまったく意識が及ばなかったのは、それが原因だった。また妻のがんが、喫煙とは関係がないとされる腺がんだったことも、かれの想像力にブレーキをかけていた。
妻の死からひと月ほどがたったある日、鼓は悲しみを紛らせたい思いからSNS上で彼女の死について告知した。
かれは退職後に暇を持て余してSNSを始めた。10年あまり前のことだ。まもなく70歳代も終わろうとする今も、鼓は日々の出来事を発信しSNSの友の投稿を楽しむ。
その中に喫煙や受動喫煙が肺がんの原因のひとつという説もありますね。奥様は煙草をおすいになったのでしょうか?という書き込みがあった。
鼓が家の中でも煙草をすっていたころ、妻が子供と自分の受動喫煙についてうるさく文句を言っていたことがあざやかに記憶によみがえった。
同時に妻の肺がんが、あるいはかれのすう煙草からの受動喫煙によって形成されたかもしれないと気づいた。
40年ほど前の、煙草をめぐる自分と妻の確執を思い出して鼓は胸が苦しくなった。
当時、典子がますます口うるさくなったのは、俊行が日本に帰ってからのことだった。酒はいい、煙草だけはやめてくれ、と主張する典子に、いややめない、禁煙がはやっているから俺も煙草を断つというのは主義に反する、と鼓は言いかえして夫婦はことあるごとに言いあらそっていた。
鼓は性格的に、大勢が右に向かうから自分も右に顔をむける、ということができない。主義に反する、というのは少しおおげさだが、世の中の風潮が禁煙にかたむいているからといって、やめたくもない煙草を断つのはいやだ、というのはかれの本心である。しかし、こと禁煙問題に関するかぎり、妻と俊行への反発心がかさなって彼は必要以上にかたくなになっていた。
義弟の俊行は半年前に5年間のアメリカ留学を終えて帰国した。アメリカでは彼は映画の勉強をしてきた。それをいかして仕事をしたいらしいが、斜陽と言われてひさしい日本映画界にはなかなかうまい就職先はない。当面はフリーの助監督として、テレビの仕事をしながら食いつないでいる。フリーといい、助監督と言えば聞こえはいいが、フリーとは不定期にしか仕事がはいらない、潜在失業者のことであり、助監督とはプロの映画作りを実地に勉強させてもらう雑用係といったていどの職業である。収入はほとんどない。ところが良くしたもので暇な時間はたっぷりとある。そこで彼はアメリカ仕こみの英語力をいかして通訳や翻訳のアルバイトをしながらどうにか生活をしていた。
帰国した早々から彼は、アメリカではまともな人間は煙草をすわない。義兄さんも禁煙をして1日も早く文明人の仲間入りをするべきだ、と鼓の顔を見るたびに言いつづけていた。
「ほんとよ。広いお屋敷にでも住んでいるならともかく、こんなにせまい家なんだから、少しはかんがえてほしいわ。家族の全員が自分の煙草の煙でひどい目にあっていることなんか、まるっきり頭にないんだから」
「かなわないな、きょうだい2人に嫌われちゃ。それでなくても姉さんは煙草ぎらいなんだから、あんまり彼女に入れ知恵をしないでくれよ」
鼓は俊行が帰ったばかりのころこそおおように構えていた。妻のぐちを聞きながして、笑ってそういう余裕があった。最近では少し事情がちがう。
煙草をめぐる典子のぐちやいやみが日一日と多くなり、トゲトゲしさが増していた。いわく、あなたが煙草を2本すえば、周囲の子供や私はほしくもない煙草を1本分すいこむ計算になるのよ。家族をみなごろしにしたいの。いわく、肺癌になるのはあなたの勝手だけど、家のローンの返済と子どもが大学を終えるまでは死んでも働いてもらいますからね。いわく、煙草のひとつもやめられないような意志薄弱な人間は会社での出世は望み薄と言うわね。あなたもきっと課長どまりで定年ということだわ。結婚する相手をまちがえてしまった・・云々。
典子はもともと煙草がきらいな女だった。煙草ぎらいな女に色気のある者はいない、というのが鼓の持論である。それを承知で彼は典子といっしょになった。だから彼女の色気のなさと、喫煙に対する時たまのぐちやいや味はがまんする。しかしそれがのべつ幕なしに耳に入ってくるとさすがに腹にすえかねる。
典子がそうなったのは、俊行が家にやってきて、鼓に禁煙をさせろ、と彼女にしきりに入れ知恵をするからである。喫煙者と肥満体の男は出世できない、という本当かうそか知らないアメリカの話を織りこんで典子が不満を言うのも、俊行に感化されてのことだった。
俊行は鼓の家から歩いて10分もかからない場所に住んでいる。住まいが近いうえに、アパートでゴロゴロしながら翻訳のアルバイトをしていることが多いから、彼はひんぱんに家に遊びにやってきて、典子に禁煙のススメを説いて聞かせているのである。
「アメリカで煙草をすっているのは黒人をはじめとする有色人種だけだね。白人、特に上流階級の白人はみんな煙草をやめているよ」
休みの日の昼食時を見はからって俊行が来ている。俊行と典子は仲がいい。幼いころに両親をなくしていることもあって、身寄りはたった1人の姉弟だけだとおたがいに親しみあっている。そういう2人の間がらだから、鼓は典子を通してはやくから俊行をよく知っている。かれのアメリカ留学に際しては物心の両面にわたって世話をやいてやり、帰国したらしたで礼金と敷金を用意して自宅ちかくにアパートを借りてやったのも鼓である。まだ就職の当てもない弟を心配する典子の強い申し入れもあったが、鼓が俊行をきらっていたらむろんそういう事はおこりようがなかった。
鼓自身に兄弟がない事情も手つだっているのか、かれははじめから俊行に対しては保護者でもあるかのような親しみを抱きつづけてきた。それはいまも変らない。煙草の件で俊行にすこし腹を立ててはいるものの、彼の気持の底には、血を分けた兄弟でもない鼓に「禁煙をしろ」とズケズケ口にする俊行の率直さをよろこんでいる部分があるから、怒りには典子へのそれとはちがって、はなはだ迫力に欠けるところがあった。
それでも話がまたしても禁煙のことになると、鼓の気分はおだやかではなくなる。
「残念ながら俺は有色人種で、しかも上流階級じゃないんでね。煙草をやめる理由もしたがってない、ということだ」
牡蠣フライを口にはこびながら、彼はむっとして俊行に言いかえした。
昨夜はつき合いでしたたかに飲んだ。飲むとたちまち煙草の量が増える。喉から肺にかけて、ひりひりと焼けるような痛みがかかっていた。こういう日は朝起きてからしばらくの間は煙草をすう気になれない。会社のある日でも午前中はすわずにいて、昼食後にまず一服、ということになる。
今日は土曜日である。週休2日制の会社はやすみだ。鼓は12時過ぎまで寝ていて、1時前にはじまった食卓に家族とともについているところなのである。それまで煙草のことをおもいだすだけで胸がむかつく気分だった彼は、俊行の話にたちまち反発心を呼びおこされて、無理をしてでもすってやる、とおもった。
「別に人種差別のつもりで言っているんじゃないよ義兄さん。アメリカでは収入の多いインテリ層の人たちは、健康への関心が高くて禁煙するケースが多い、というだけさ。たまたま黒人や有色人種は低収入の層に属していて、しかも喫煙者の数が圧倒的に多いということ」
「俺はブルーカラーじゃないかもしれないが、だからといって上流階級でもないね」
鼓はむきになって俊行の言葉尻をとらえて踏んばる。
「この貧しい日本国で、大昔から週休2日制を敷く余裕があった大会社の課長はりっぱな上流階級だよ義兄さん」
俊行は別に揶揄する気もないらしいきまじめな顔で、箸で宙を突きながら反論する。
「上流階級?お金もないのにばかなことを言わないで、俊行」
典子が鼻でわらった。
「金がありあまっているという意味ではなくて、インテリで高給取りでホワイトカラーで、ということ。りっぱな上流階級だ」
「どうだか。大学を出ているのだからインテリでホワイトカラーというのは百歩ゆずってみとめるとしても、絶対に高給取りじゃないわ。煙草代が家計にひびく程度の給料取りよ」
典子が冗談めかしたつもりで口元だけのゆがんだわらいをうかべる。牡蠣フライとご飯と新香が口中で唾液にからんでいるのが見えた。
「そりゃそうだ。高給取りの女房はたいてい品良く飯を食うものさ」
鼓は悪態をついた。
アメリカ、アメリカと題目でもとなえるみたいに言う俊行もしゃくにさわるが、おもいやりというもののひとかけらも見えない妻の態度にはもうがまんができない。この場で堂々と1本すってやる、と居間に置いてある煙草を取りに行きかけてかれは思いとどまる。娘の香織が両親のとげとげしいやり取りに困惑して、箸をとめてじっとこちらを見つめている。彼は娘のために、これ以上のいさかいをしないことにした。それでなくても昼食はすっかりぶちこわしになっていた。
騒ぎの発端になった俊行は、ずぶといのか単に鈍感なだけなのか、すこしもあわてないで食事をたいらげた。食べ終えるとすぐにべそを作って落ちこんでいる香織を居間にさそって、なにごともなかったかのように遊び相手になってやっている。
典子はあそぶ2人の脇のソファにすわって、次女の由樹にミルクを飲ませはじめた。
鼓は、ガラス戸でしき切られた居間の縁側にすわって一服している。居間から追いだされたようではらだたしいが、妻の腕のなかで無心に哺乳瓶の乳首をすっている赤ん坊を見ると、とても部屋のなかで煙をまきちらす気にはなれなかった。いくら注意しても煙をあらぬ方向に吐きだしても、せまい居間の空気はみるみるうちによごれていくのがわかる。子供の小さな体に毒をふきこむようでかれは落ちつけなかった。
「アメリカに行ってすぐに煙草をやめたのか、俊坊」
鼓は縁側から声をかけた。昔からの習慣で鼓は彼を俊坊と呼んでいる。
「2年ぐらいはむこうでもすっていたよ。なかなかやめられなくて禁煙にはずいぶん苦労しました」
俊行も以前は煙草をすっていた。鼓と同じブランドの煙草だ。すい始めたのはちょうど鼓と典子がいっしょになったころのことである。当時かれは2人のアパートにひんぱんにやってきては、わがもの顔で鼓の煙草を失敬していた。若いから粋がるところもあったのだろうが、あの頃は俊行のほうが鼓よりもよっぽどヘビースモーカーだった。
「このあいだも言ったでしょう。煙草なんかすってるとバカにされるからだよ。体にはわるいし、女の子にはもてないし」
鼓は2本目の煙草に火をつけた。食卓でのやりとりりに腹をたてて、これ見よがしにはじめの1本に火をつけたときは、胸が焼けるような不快感があった。不快感はずっとつづいた。それでも1本をすい終えると惰性で次の1本に手がでた。はじめの1本ほどの胸のむかつきはない。が、しびれた肺に棒を差しこむようないやな感じがのこる。
左手の中指と人差し指でフィルターをはさみ、その端を親指でおさえて立ちのぼる煙を見ながら、(こんなもの、いつやめてもいいんだが…)と彼は胸のなかでつぶやいた。
鼓の会社でも禁煙に踏みきる者が増えている。最近の例では常務の市村がそうである。市村は近い将来、同じ常務の平沢と社長の座をねらって競い合うと目されている実力者である。彼が禁煙をしたというニュースは、その日のうちに社内を駆けめぐった。それから1週間も経たないうちに、営業三課長の田代も禁煙に踏みきった。田代は早くから社内では市村寄りを表明している男である。彼はボス禁煙の話を聞いて、すぐにそれを真似することにしたらしい、というジョーク交じりの噂が立ち騒いだ。
酔って帰った晩、鼓はとなりに寝ている典子に手をのばした。典子はとたんに体をかたくして、
生後8ヶ月の由樹は典子のむこう側の子供蒲団に寝かされていた。夫婦はここ2ヶ月ちかくも交渉を持っていない。鼓の帰りが毎晩おそいこと。つかれていること。典子にそのことへの不満がないように見えること。時をかまわわず泣きだす赤ん坊への遠慮…さまざまな理由があった。が、いちばん大きな理由は、なんといっても煙草の件で夫婦が言いあらそいをくりかえしているところにあった。
鼓はものごとを根に持つたちではない。夫婦喧嘩のときも花火のように感情をたかぶらせて、あとくされがないのがふつうである。煙草のばあいもやめろ、やめない、で典子といがみたったあとは、きれいさっぱりと忘れてしまいそうなものだが、なにしろ煙草は毎日口にくわえるものである。典子はそのたびにひと言いわないと気がすまない。鼓は言われるとだまっていない。結果はのべつまくなしに花火が爆発している、といったぐあいになる。
たまに典子が1人で起きて鼓の帰りを待っている日がある。そんな日は彼女は、帰宅して煙草をふかす夫を見ても見ぬふりをしている。そうなると鼓は、妻の沈黙が気になってしかたがない。わざとらしいと思う。照れる。彼のぎこちない心理状態は典子にもつたわって、2人はおたがいにいよいよ気が張ってくる。夫婦のことだから、余計なことをかんがえずに彼女にのしかかっていけばすべてうまくいくはずなのに、彼はぐずぐずしている。タイミングがおかしくなる。やがて典子がそっぽをむいて自分の蒲団にもぐりこむ。鼓はそれを見て、なぜかむっとした気分で彼女につづく。そんなことがくりかえされていた。
無視して、妻の胸をまさぐって、身をおこして彼女の上におおいかぶさった。顔をつきだして典子の唇をさがす。典子はふいのことにおどろくのか、眠りを中断されて不機嫌になるのか、さらに体をかたくして抵抗する。鼓は高まってひるまずに動きをつづけた。
「やめてよ。煙草くさい」
低い、するどい声で典子が言った。言っておいて、しまった、というふうに口に手をあてている。鼓は体の芯に電気を通されたようなショックをうけた。一気に萎えて、腕立て伏せを中途でやめたような格好で彼女の上に体をとめた。
かれは相手の気持を誤解して先走り、こっぴどく拒絶された思春期の少年のようにとまどっていた。
その気になればいつでも押し入ることができる、と思いこんでいた妻がひどく遠い存在にかんじられた。がくりと右腕をたたんで、寝がえるように自分の蒲団にもぐりこんだ。屈辱感が強烈にかれをおそっていた。
煙草をやめよう、と鼓が決心したのはそれから間もなくのことである。
無数にでてくるいざこざ、小言の投げあいのひとつ、とかれが高をくくっていた煙草の件は、その夜を境に夫婦の間に不透明ないやな緊張感をもたらしていた。
典子は翌日から煙草のことをいっさい口にしなくなってしまった。俊行もおなじである。かれが鼓と顔を合わせて煙草の話を持ちださないのは、帰国以来はじめてのことだった。あきらかに典子に口どめをされている。すべてての気づかいがよけいに彼の気をおもくした。このままほうっておけば、妻との間に埋めきれないふかい溝ができてしまう、とかれは不安になった。
朝目がさめると鼓はまずちかくに子供がいないことをたしかめて煙草に火をつける。それは寝室である日もあるし、居間である場合もあるし、あるいはトイレ内だったりする。朝食後にも1本ふかす。家を出て駅まで歩くあいだにも1本。都心で電車を乗りかえるときもたいてい1本に火をつける。混雑がはげしく、しかも禁煙地帯が多い駅の構内ではほとんどそれを楽しむ余裕はない。しかしかれはどうしても1本を灰にしないと気がすまない。通勤の最後では、地下鉄の駅から地上にむかうあいだにさらに1本を箱から抜きだす。会社に入ったあとはたてつづけに煙草をすっている、というのがかれの喫煙状態である。本数は1日にだいたい2箱から2箱半というところにおちつく。酒を飲むと日によってちがうが、その倍ちかい量になることもめずらしくない。
鼓はその日、朝起きてから会社に入るまでの5本をすんなりと断った。通勤の途中ではいつものくせで胸ポケットになんども手がのびた。そのたびに思いとどまった。
やめる決意をしてもかれは煙草とライターを胸ポケットに入れていた。腹をきめれば煙草などいつでもやめられる、と鼓は自信をもっていた。禁煙をきめると同時に煙草やライターを捨ててしまうのは、自信のない人間のすることである。彼の自負心は煙草の煙が充満している社内に入ってもゆらがなかった。鼓はいつものように煙草とライターをデスクの上において、悠然と仕事をはじめた。
10時半から会議がはじまった。せまい会議室には換気口に入りきらない煙草の煙が、朝なぎの海の霞みたいにしばしば上空にただよった。会議に出席している管理職の多くが喫煙者である。禁煙した重役の噂が社員の関心を集めたりもするが、やはり煙草のみの数は多い。
頭のなかにぬるい薄い霧がたちこめるような感じがまずあった。かれは血圧が低くて朝はよわい。朝起きてしばらくのあいだ、かれの頭のなかは今のようにはっきりしない状態になることがある。
霧がふいに濃くなって一瞬まっくらになった。左手に奇妙な感覚がある。手の甲を枕にうたた寝をしてしびれた時のようである。しびれは間もなく小指に集中して、そこだけがぴくぴくとけいれんした。が、見た目には小指にはなんの変化もない。そんな感じがするだけなのである。鼓はあたりをはばかりながら、なんの異常も感じていない右手の親指と人差し指でそれをはさんで軽くマッサージをしてみた。
感覚がなくなっている。不安になった。つづいて頭の内側を大きな輪ゴムかなにかでぎゅっとしめつけられるような刺激がはしった。痛みというのではない。頭の機能を停止させる魔術にでもかかったみたいな、薄気味のわるい圧迫感である。
一連の変調が地震のように次々に体内をはしった。と思う間に輪ゴムがゆるむ。強風にふかれるように霧がすっと晴れた。頭のなかが涼しくなる。しかし左手小指にはビニールをかぶせたようなしびれ感がそのまま居すわってしまった。
鼓は営業2課の自分のデスクにもどって、会議室で配られた30ページあまりの書類に目を通しはじめた。
ふいに頭のなかに霧がわいて、小指がぴくぴくとけいれんした。輪ゴムがぎゅっとくる。目は書類の文字を追っているが、意味がまったくつかめなくなった。左の小指を右手でもみほぐそうとムダな努力をしながら、おなじ行をなんども読みかえす。あせりがこみあげて頭のなかは混乱するばかりである。
急に煙草がほしくなった。同時にこれがニコチンの禁断症状だと気づいた。禁煙に入って10日ほどは相当につらいという話はよく耳にしていた。が、実際にどうつらいのかは鼓はしらなかった。これがそうだとはじめて納得した。
2度目の発作は会議室での最初のそれよりも長くつづいた。手のひらに脂汗がにじみでている、と鼓が気づいたとき波がかえすように霧がはれた。頭の内側の圧迫感が消える。が、小指にはやっぱりしびれがのこった。
はじめのときは発作へのショックがかさなったせいか、前後に大きな落差をかんじた。発作のあとでは頭のなかが凛と冴えわたるような気がした。今回は余韻がうすい幕を張ったようにのこってすっきりしない。煙草への欲求が耐えがたいくらいにつよくなった。それを振りきって鼓は書類の文字に集中しようとした。2頁ほど読みすすんだとき、再三発作の波がおしよせた。
書類は緊急に目をとおして、他の課の責任者にまわさなければならないものである。かれはいらいらして大声をあげたくなった。ふと見ると、係長の吉川が部下のデスクに寄って、なにやら話なしがらうまそうに煙草をふかしている。駆けだしていって煙草をうばいとり、おもいきりけむりをすい込みたい衝動におそわれた。
鼓は自分に言いきかせた。飢えたハイエナみたいにあわてて煙草の箱から1本を抜きだして口にくわえた。一服する。かすかに目がくらんだ。2度目に煙草をすい込んだときは、ニコチンがじわと血管にしみとおるのが見えるような気がした。吐く間ももどかしく、鼓は煙を深々と肺に送りつづける。頭のなかのもやもやが吹きとんでさっぱりした。小指のしびれ感も嘘のようになくなっていった。
書類の言葉の流れがすらすらと頭に入る。彼は文章にまぎれこんでいる誤字に気づく余裕さえ出てきた。
2本目の煙草に知らずに手がのびた。鼓は気づいてちょっとためらった。せっかくここまできたのだから1本でがまんしようか、と自問した。
(しかしまた発作が来たらたまらない。それに1本すってしまえばもう同じだ)
その後はとめどがなかった。鼓は結局、退社時間までにいつもよりも多めの3箱60本の煙草を灰にしていた。
明日からもう一度出なおしだ、とかれは帰りの電車の中でつぶいていた。その日はじめて体験した禁断症状がすこし気になっていた。が、まがりなりにも朝からしばらく煙草を断つことができたのがなぐさめになっていた。重要書類に目をとおさなければならなかった不運さえなければ、今日1日煙草なしで済ませられたような気もした。前途はあかるいとおもった。
鼓の胸ポケットには地下鉄の駅で買った煙草が入っている。彼は電車を待つあいだに箱をあけて、すでに1本を抜きだしてすった。会社がおわった時点で再び禁煙をはじめてもよさそうなものだが、鼓はどうせならもう1度朝からやりなおしたかった。物事にははじまりのタイミングがある。1年の計は元旦にあり。長年慣れしたしんだ煙草を断つという大事業は、きっぱりとけじめをつけて朝から開始しなければ、かれはどうにもおさまらない気がした。
「ああ。仕事のあとで麻雀にさそわれたがことわってきた。俊坊、来ているのかい」
玄関に俊行のスニーカーが脱ぎおかれている。長身の俊行は足も大きく、スニーカーはすぐに彼のものとわかる。
ふりむいて彼は返した。立ちどまる夫にふいをつかれて、典子の体はかれの胸にぶつかった。
あわてて言う彼女の顔が上気していた。くるりと背をむけて小走りにキッチンに消えた。まるで小娘のようなうしろ姿だと鼓はおもった。
俊行といっしょにテレビを見てた香織がいちはやく鼓に気づいてさけんだ。
「あれ。早かったんだね義兄さん。どうしたの?」俊行は相変わらずのんびりしている。「早めに電話でもくれれば,夕食を待っていっしょに食べたのに」
まるで自分の家にでもいるみたいにけろりとして言った。姉の気づかしいなんかすこしも知らない。鼓は苦笑した。こういう大ようなところが俊行の良さだ、と素直におもった。
「うん。俺もこんなに早く帰れるとはおもってなかったんでね。ちょっといっぱいやろうか」
自分の口から禁煙話を持ち出すことはぜったいにしない、ときめていたにもかかわらず、鼓は言ってしまった。少し酔いがまわって舌のすべりがよくなっていた。それでもさすがに禁煙をするとはいわず,本数を減らすという言いかたをした。
典子が横あいから身を乗り出した。彼女は今夜は機嫌のいい鼓に影響されてうきうきしている。いつもなら「どうせ口先だけでしょ」「3日ももてば上等だわね」という類のにくまれ口をたたくところである。
鼓は頭をかいた。ぜったいに煙草はやめない、とがんこに言いつづけてきたかれである。たちまち禁煙宣言をするのは気がひける。
「だめだめ。そういう中途半端なやりかたは絶対にだめだよ義兄さん。煙草はここできっぱりとおさらばするか、すいつづけるかのふたとおりしかない。禁煙は引き算じゃないんだ。数を減らしていって最後にはゼロにしようなんてやりかたじゃ成功しない。白か黒か、それしかないよ」
俊行は断固としてつっぱねた。それはいい考えだ、とはげます気なんかこれっぽっちもない。
「そうかな。すこしずつ減らしていけばそのうちにはやめられるんじゃないの」
俊行の好意的な反応をすくなからず期待していた鼓はがっかりした。
「煙草はね義兄さん、1本すっても30本すってもおなじ毒なんだよ。とくに長いあいだすっている人間にはね」俊行はあわれむような声になった。「数がすくなければ体には毒がすくないという話を聞くけど、あれは煙草会社の陰謀だよ。やめるのなら、すぱっとひと息にやめるべきだ」
「今すぐにやめようという気にはなれないんだ。煙草は好きだからしょうがない。すこしづつ本数を減らしていって、その気になればやめるさ」
鼓は内心、いまにびっくりさせてやるから見ていろ、といたずらっぽく考えながら、わざと気おちした声を出した。
鼓は5時間後に目がさめた。それ以降も前日とおなじように煙草を断ちつづけた。
いつのまにか係長の吉川が鼓のデスクの前に立っている。鼓は無意識のうちに左の小指を右手で包むようにしてもみほぐしていた。
彼は気づいて、あわてて手をはなした。ふと見ると、部下の1人ひとりがそれぞれの机の前にすわっていぶかし気にこちらをながめている。どうやらかれは知らずに長いあいだそうしていたらしい。ひや汗が出た。
吉川がデスクのはしに置かれている清算書をかれに押しやった。それは先刻かれが鼓の認印をくれと言いのこしておいていったものである。
鼓はそのことをすっかりわすれていた。かれがいつまでも書類に目をとおさないので、吉川はようすを見にやってきたものらしい。
ぱらぱらとそれをめくりながら、右手を煙草の箱にのばした。1本をぬき出して口にくわえる。火をつけるつもりはなかった。口にくわえていれば気がまぎれると思った。煙草をくわえたとたんに、吉川が自分のライターをさっと出して火をつけた。考える間もなく、鼓は顔を前につき出して煙草の先を火のなかに入れた。
しまった、とおもった。よけいなことをするな、と言いかけて、ぐっと言葉をのみこんだ。部下の親切をあだで返してはしめしがつかない。ままよ、と一服深々とすいこんだ。たちまち気がはれて、世の中があかるく見えた。
それから先はタガがはすれたように節操がなくなって、鼓は次々に煙草をぬき出していた。
次の日は昼食までふんばった。社員食堂でカツ丼をたいらげたとき、猛烈に煙草がほしくなった。腹がふくれるとかれはいつも一服したくなる。それをよく承知しているから、鼓はわざと煙草をデスクにのこしてきていた。手元にないとよけいにすいたくなる。逆効果もはなはだしい。茶と水をがぶ飲みしてまぎらそうとした。無駄である。気がおかしくなりそうになった。
ふと見まわすと、営業三課所属の顔見しりの若い社員2人が、食事をおえて極楽顔に煙草をふかしている。鼓は矢もたてもたまらなくなって席を立った。
鼓がそれをぬき取ると、あとのひとりがすかさずライターの火を差しだした。
一服の力はあいかわらず絶大である。鼓はたちまち生きかえった。
11時から昼食にかけての時間帯にかれはいつも挫折した。朝起きてから会社に入るまでのあいだをうまくきりぬけて、今日こそは、と誓いもあらたに鼓は仕事をはじめる。仕事はいつも山積している。頭のなかが霞がかったようにはっきりしなくなり、目まいまがいの症状がやってくる。こらえて仕事をすすめる。11時を過ぎるころになると仕事の遅れが目だってくる。いらいらする。鼓はこらえきれなくなって、急ぎニコチンを取りこむ。なんとかそこを切りぬけても、昼食後にはやはり誘惑に負けて煙草に火をつけてしまう日がつづいた。
ウィークデーの失敗にこりたかれは、土日のやすみを利用して禁煙を達成することにした。なにはともあれ1日24時間を完全に禁煙することが大事である。週末のどこかでそれができれば、あとは水が川を流れるようにスムーズにことが運ぶにちがいない。
決意もむなしく、土曜日は接待ゴルフにつきあわされて鼓はあっけなく禁をやぶった。
煙草の煙が充満する会社とは別世界の、空気の澄みきったグリーンに足を踏みこむやいなや、かれは禁煙の誓いを先にのばしたくなった。ぐっとこらえてコースを回りはじめた。発作が起こってクラブをにぎる手がおぼつかなくなる。それでもがまんした。
クラブハウスに入って屋外でビールを飲んだ。すきっぱらにアルコールがしみ込む。接待相手のふかす煙草の煙が風にふかれてかれの目の前にただよってくる。鼓は鼻の穴をそっとひらいてそれをすいこんだ。せつなくなって1本に火をつけた。汗をながしたあとの煙草は格別な味がした。
鼓は10時に目がさめた。ゴルフ疲れでよく寝たせいか爽快な気分である。近来めずらしいすっきりした朝だ。禁煙に挑戦していらい、さすがに煙草の本数がへっている。おかげで体調がよくなったのか、とかれはおもう。
遅い朝食をとった。食べたあとも食卓にのこって新聞に目をとおしていた。さっそく煙草がほしくなる。体調がいいとそれに並行してニコチンへの欲求も強くなるものらしい。いつにもまして不満感がつのる。ぐっとこらえつづけた。
昼前に1人で散歩に出た。駅の踏切をわたって、線路ぞいの民家の前をしばらくあるいた。ところどころに茶畑が見えてくる。このあたりまでくると、家と空き地が日に焼けて皮のむけた背中みたいに勝手気ままな配置でひろがっている。雑木林や竹林も多い。そのあたりもやがては造成されて家が建つのだろう。
犬を連れた初老の男が、茶畑のなかのいっぽん道をこちらにやってくる。煙草をふかしている。犬に引かれて立ちどまる。白い小さな棒の先からひとすじの紫煙が立ちのぼて大気に飲みこまれていく。そこまで気がまぎれていた鼓は、また煙草がほしくなってしまった。苦しい。男とすれちがうとき、よほど声をかけて1本分けてもらおうかとおもった。かろうじて耐えた。
禁断症状は判で押したように一定の間隔をおいて高波になって寄せてはまたかえしていく。すくなくとも会社のなかの限られた空間で、他人のふかす煙草の煙に巻きこまれるばあいはそうである。ところがゴルフ場や戸外の散歩道のように気のまぎれやすいい広い場所にいると、発作は不規則にやってくる。それにはきっかけがある。煙草をすっている他人を間近に見たときである。ひとのあくびを見て眠気をさそわれるのに似ている。こまったことに禁断症状は眠気とはくらべものにならない苦しみをもたらす。特にふいの発作の場合には、前震のまったくなかった大地震のようである。エネルギーがたまっていっきに爆発するから苦しみが大きい。
男をどうにかやりすごしたものの、鼓は体内にかんしゃくもちの子供が飛び込んで駄々をこねているような、掻くにかけないつらい気分になった。目の前が闇になり、左手がしびれてすぐに小指に集中する。いてもたってもいられなくなった。
手のとどく道沿いに茶の葉がしげっている。茶の葉っぱにはカフェインがふくまれている。カフェインもニコチンも同じアルカロイドである。親戚のようなものだ。どこかで読んだ知識が、鼓の脳裡にうかんだ。次の瞬間にはかれは右手いっぱいに茶の葉を引きちぎっていた。口に押しこんでむしゃむしゃと噛む。たちまち苦味が舌を刺した。
鼓はわれにかえった。噛みくだいた物をあわてて吐きだした。腹が立った。こんなにみじめな思いをしてまで煙草をやめる必要があるのか。たかが煙草だ。好きなだけすってやる。彼は急に気が大きくなった。
帰る道すがらあたりをかまわずに唾を吐きつづけた。が、口中の苦味はなくならない。家に着いて洗面所でなんどもうがいをした。最後に歯を磨くとようやく人心地がついた。
口なおしのつもりで縁側に出て一服した。すうはなから後悔した。何かと理由をこじつけては結局禁断症状に負けているだけだ、と苦くおもった。
典子が庭の物干しに洗濯物をかけながら横目でこちらを見ている。嫌悪感が表情に出ていた。
(今日はじめての煙草だ。文句があるか。俺だって苦労しているんだ)
彼は妻の横顔をにらみつけておもった。たてつづけに煙をすいこんだ。
鼓は会社の昼休みに本屋に寄って、『禁煙法教えます』という本を買った。先ごろ煙草を断った部下のひとりが、それに書かれている方法を実践して禁煙に成功した、という話を耳にしたのである。
『禁煙はニコチンによる中毒である。その意味では麻薬と同じだ。まずそのことをしっかりと認識すること。それが禁煙を成功させる第一の、そしてもっとも重要なステップである』
図柄入りの本はそんなふうにはじまっている。煙草がなぜ体に毒なのか、という医学的な事実を具体的にわかりやすく説いたあとで、本はさらにつづける。
『禁煙には徐々に本数を減らしていく方法と、ひといきにすぱっとやめる2通りの方法がある。ひといきに禁煙に踏みきるのは意思の強い人間のやり方だという考えが喫煙者のなかには根づよくある。それは完全なる誤解である。なぜならば煙草は1本すうと止めどがなくなるのが中毒たるゆえんである。したがって毎日まいにち正確に本数を減らしていくこと、-つまり1日にすう本数を決めてそれを順守すること‐は実は至難のわざである。それができればこの本を読んでいるあなたは、ニコチン中毒などという悲惨な病気にかかることはなかったはずだ!漸減法はふつうは計画どおりに事がはこばず、あるていど本数を減らすとなかなか前にすすまないことが多い。たとえ計画どおりに行っても、完全に煙草を断つ最後の段階ではいっきに禁煙に踏みきる場合とおなじ苦痛がともなう。禁煙は本数の問題ではなく、すうかすわないか、白か黒かの問題である』
『煙草は右のような理由で、いっきにやめてしまうのが合理的であり、かつ容易な方法である』
本はそう結んだあとで21ヶ条の禁煙心得をしめす。そのおもなものは簡単に言うと次のごとくである。
一.禁煙を決意したらすぐに,家族や友人や同僚をはじめとするすべての知人に高らかに禁煙宣言をしろ。
- ただちに煙草・マッチ・ライター・灰皿等の喫煙器具を屑かごになげ捨てろ。
- 喫煙者にキスをするのはよごれた灰皿をなめるようなものである。勇気を持ってこのことを恋人に伝えろ。
- 左の写真をいつも頭に描け。これがあなたの肺である。(癌におかされてただれた肺の切断写真)。
- どうしても煙草がすいたくなったらガムやハッカキャンディーを口にふくめ。冷水で顔を洗え。うがいをしろ。歯をみがけ。からだを動かせ。深呼吸をしろ。走れ!
- 煙草の害は肺癌にとどまらない。あらゆる業病難病の元をなす。エイズもニコチンに関係している可能性がある。このことを常におもい出せ。
- 子供・恋人・愛人・妻にペット・・…愛する者のことをかんがえろ。かれらは知らずにあなたの煙草の煙につきあって墓場をめざして一直線に歩いている。云々―。
自己暗示のためのモットーのようなものもあれば,具体的な行動指針を示すためのものもある。
鼓は21ヶ条の中でも冒頭にかかげられているふたつにもっとも抵抗をおぼえた。かれはふだんから家族や会社の同僚にむかって、ぜったいに禁煙はしない、と大見得をきってきた。だから意地でも禁煙宣言はしたくない。典子と俊行には酔ったいきおいで煙草の本数を減らすと言ってしまったが、あれはあくまでもはずみでそうなったのである。禁煙はどうしても人知れずに達成したかった。 同じ理由でかれはふたつ目の心得にも感心しない。なぜならば煙草やライターを捨てて、会社のデスクにある灰皿を処分すれば、それは即座に周囲の人間に禁煙宣言をするようなものである。それはこまる。結局かれははじめのふたつを飛ばして、残りの心得に気をくばってみた。ほとんど効果はなかった。それでも本にこだわっていたあいだに1日半だけ禁煙に成功した。大阪出張に出たときのことである。
鼓はその日、朝7時の新幹線で大阪にむかった。起きてからずっと煙草を断った。列車の座席は禁煙車両のそれを買っていたから、その中でもすわずに済ますことができた。またその気も起きなかった。周囲に煙草をすう人間がいないと禁煙はいつもたやすい。
大阪支社につくと、彼は聞かれもしない前から「禁煙中」だと言いふらした。大阪には鼓が禁煙反対論を唱えていたのを知る者はいない。だから彼は大いいばりでそう口にすることができた。大阪でも禁煙ははやっているとみえて、誰もかれの言葉を聞きとがめなかった。「お、やりましたね」「それはいいことですよ」「うらやましい」私もやめてしまいたいが、なかなか」というぐあいに、むしろ好意的な反応ばかりがかえってきた。たとえ口にはださなくても、誰もが賞賛するようなまなざしでかれを見る。鼓はその日は心なしか、間断なくおそってくる禁断症状がかるいようにおもった。
夜は支社長の塚原と総務部長の戸山にさそわれ飲みにでかけた。鼓は飲むとかならず煙草がほしくなる。しかし昼間のうちに2人に面とむかって、禁煙1週間目ですと話していた手前、かれははじめけんめいに欲求をこらえた。酔って気がゆるむとどうでもよくなった。鼓は隣にすわっているヘビースモーカーの戸山の煙草をなんども失敬しようとした。そのたびに塚原が、せっかく1週間も禁煙したのだからもったいない、がまんしなさい、とかれを制止した。塚原は東京本社にいたころに煙草をやめたのだという。
「1週間から10日目ぐらいが1番きついんだ。もうすこしのしんぼうだよ。戸山君、せっかくかれががんばっているんだから、今夜は隣でぷかぷかふかすのはやめたらどうだい」
「そうですね。大阪出張で禁煙がだめになったとあとで鼓君にうらまれちゃかなわない」
戸山は和気あいあいにかえして、使いすてのライターと煙草をまとめて、
「お、いいですね。男の友情、武士の情け。戸山さん泣かせますね」
バーテンダーはつまらないことを口ばしって、受け取った物を足元の屑カゴに投げこんだ。鼓はしかたなく戸山と塚原に礼を言う。
アルコールと煙草、コーヒーと煙草、という2つの組み合わせは、いつもくっついていないと鼓は不安になる。ニコチンをほしがる体をなだめようとして、かれは次々に水割りのグラスを口にはこんだ。その夜は正体をうしなうほどに酔った。
ふつか酔いの体は一転して煙草を拒絶する。翌日の午前中は鼓は煙草に手を出す気になれなかった。午後には大阪での仕事を終えてひとまず東京の本社に電話を入れた。部長の山倉が電話に出て、今日中に出張の報告を聞きたいから会社に顔を出してくれという。部長命令では仕方がない。鼓は予定よりも早めに新大阪に向かった。新幹線の中ではぐっすりと寝込んだ。おかげで煙草は気にならなかった。
鼓はためらうことなく返した。列車の中で寝たおかげでふつか酔いからはすっかり立ちなおっていた。気分がいい。山倉が大阪での仕事の成果を気に入っている、と分かったころから彼はしきりに煙草をおもいだしていた。仕事がうまくはこんだあとの煙草の味にも格別なものがある。が、彼はその場はぐっとこらえて切りぬけた。
山倉がふいに聞いた。彼の行きつけの寿司屋で、食事がてらに飲んでいた最中のことである。鼓はぎょっとして、ほおばっている握りをひといきに飲みこんだ。山倉は大の煙草好きで、だからというわけではないが、社内の派閥抗争では喫煙派の平沢常務に付いている。山倉をはじめとする平沢派の人々は、禁煙に踏みきった市村常務とその一派への対抗心から、最近しきりに喫煙者と禁煙者を区別して色眼鏡で見ていると言われていた。むろん対抗者どうしをきわだたせるためのジョークだろうが、山倉の口から煙草の話がでると妙に空気が重くなった。
「いえ。そういうわけでもないんですが。ちょっと、その、煙草を切らしちゃいまして」
山倉はカウンターにおいてある自分の煙草を彼の前に押してよこした。
「すみません。じゃ、1本いただきます。ちょうど買おうと思っていたところなんです」
鼓はすらすらと嘘をついた。山倉の煙草の1本を取り出しながら、同じ銘柄のひと箱を板前に注文した。
しばらくぶりの一服はなんともいえない味がした。ティッシュペーパーにこぼれたインクのようにすみやかに、ニコチンが肺から体の全体に浸透していくのがわかる。アルコールといっしょだから効果のほどは一段とすばらしい。
「最近どうも社内に禁煙者が増えているようだね。日本人は何でもすぐにアメリカのまねをしたがる。いったいいつになったら猿まねの癖をなくすのか、こまったものだ」
山倉はことさらに眉をひそめていった。彼が非難しているのは、もちろん市村常務とその取り巻きにちがいない。
「自他ともに愛煙家を認めている君まで、煙草をやめてしまったのかとおもったよ」
「とんでもないですよ部長。こんなにうまいものはやめられません。長年つき合ってきた煙草をあっさり捨てるのは、私にはどうも嘘っぽくて理解できませんね」
鼓はつい山倉にこびてしまった。長いサラリーマン生活のあいだに習い性になってしまった保身術は、煙草と同じで中々やめられない。
大阪支社には市村常務の「禁煙事件」にまつわる東京本社内の最近の動きはまだ伝わっていない。しかしこちらの派閥争いを反映して、むこうもすでに市村派と平沢派の色分けができつつあると言われていた。それを知りながら、大阪でうかつにも「禁煙中」だと人々に触れまわった自分の行為を、鼓はいまさらながら後悔した。煙草をがまんしていると、どうしても集中力がなくなって大事なことを見おとしてしまう。これもその一例である。
鼓は今のところ社内では市村派にも平沢派にも属さない中立の立場にいる。それでも直属の上司である山倉が喫煙派によっている事実は、鼓のこれまでの禁煙作戦にも微妙な影響をおよぼしていた。つまり彼は山倉への遠慮から、会社の中では堂々と禁煙宣言をできなかったようなところがある。いや、もちろん彼がそれをためらう最大の理由は、反禁煙を標榜していた自分の過去が気になるからである。ころりと態度を変えて禁煙バンザイとさけぶのは、転向宣言をするみたいで彼はおおいに恥ずかしい。言うならばそれは、彼の人間性にかかわる問題なのである。が、人間性をまっとうするだけでは会社という組織のなかでは生きのびられない。鼓の気持や行動の中に山倉への政治がらみの遠慮がチラと顔をのぞかせるのはどうにもしかたのないことだった。
鼓は大阪での彼のうごきが山倉に知れるときのことをおもって気が気ではなくなった。
「大阪は東京ほどアメリカの影響は強くないみたいです。ただ禁煙は世のなかの大きな流れになってしまいましたからね。若い人達のあいだにもかなり禁煙がはやっているみたいです。健康願望が強くなったんでしょうかね」
うちの社内の問題ではなく、世のなかの大勢が禁煙にむかっているのだ、と主張して鼓は自分の立場を正当化しておきたくなった。「私も健康のために少し本数を減らそうかとおもっています」
鼓はすこし誇張した。禁煙にいどんだ最初のころこそ反動で逆に喫煙量が増えたりしたが、最近では1日にすう本数はぐんとすくなくなっている。
「ほう。それはりっぱなものだ。しかし、なにも無理をして本数を減らすこともないだろう。煙草は嗜好品だ。好きなものをやめたり減らしたりしたら人間は心がまずしくなる。好きなら思いきりすいたまえ。煙草をやめてしまっても肺癌になるものはなるんだ。くよくよしてもはじまらない」
山倉は饒舌になった。酔いがまわってきたらしい。鼓はなかばは彼の言葉に賛成しながら、なかばはせっかく成功しかけた禁煙が振り出しにもどったことをくやしくおもいながら、堰を切ったように次々と煙草をふかす。こうなるとかれも酔ってきた証拠である。
新宿でテレビ映画のロケを終えたという俊行と待ちあわせて、鼓は食事がてらにかれと飲んでいた。
21ヶ条の禁煙心得の次には禁煙パイポもためしてみた。子供だましの玩具だとおも。禁煙ガムもかんでみた。会社でくちゃくちゃと口をうごかしているのはとてもがまんができずに、1時間でおわりにした。禁煙紅茶も飲んでみた。コーヒーを飲んだときのように逆に煙草をすいたくなった。紅茶という名前が良くないのだとおもった。運動をするのが良いときいて、朝の出勤前にジョギングもやってみた。走ったあとでは肺がきりきりと痛んで、たしかに煙草をすう気にはなれなかった。ところが会社に着いて仕事をはじめるころになると、胸の痛みはすっかりなくなっている。おまけに体を動かしたあとだから煙草がよけいにうまい。運動はむしろ、喫煙のすすめ、といったほうがふさわしい、とひとりつぶやいた。
結局もっとも効果がありそうなのは、禁煙心得21ヶ条のうちの鼓が避けてとおっている2つのやり方である。大阪に出張した日の成功がそのことを雄弁にものがたっている。
のこされた道は、高らかに禁煙宣言をして自分を追いこむことだ、と承知しながらかれはいぜんとしてためらっている。面子にこだわりすぎている。
サンマの塩焼き、揚げだし豆腐、焼きうどん、もつ煮こみ、アサリのバター焼き、なす田楽、とろろイモ等々の皿をテーブルいっぱいにならべてぱくつきながら、俊行は上目づかいに鼓を見る。まともな食事をするよりも居酒屋でいっぱい飲むほうがいい、という俊行の希望でふたりはこの店に来た。
「ほんとのことを言うと、すぱっとやめようとおもって努力しているんだ。挫折の連続だよ。本数はかなり減ったことはへった」
「じゃ、いいんじゃないの。兄貴はいっきにやめるよりも徐々に本数をへらしていくタイプだよ」
俊行はおごってもらっていることへの礼のつもりか、鼓に兄貴としたしく呼びかけた。
「このあいだ言っていたじゃないか。白か黒か。すいつづけるかきっぱりと捨てるか。ふたつにひとつしかないって」
俊行はこんどは鼓の目を見ようとしない。顔をふせて、立てた箸の先でとトロロイモをつつきながらいじわるに答えをしぶっている。
「――俺ね、おもうんだけど。兄貴は煙草をやめられないんじゃないかな。どうもそんな気がする」
俊行はうす笑いの浮かんだ顔を上げて、勝ちほこる調子で言った。まるで人質に死刑宣告をするサディストの誘拐犯、といったふうである。
「煙草はいやだとおもっているよ。だからやめたいんじゃないか」
「無理するなって。せいぜい体のために良くないからやめようとおもっているぐらいじゃないの。たとえばヘビとおなじくらいに煙草がきらいというわけじゃないでしょう」
「あ、そう。悪趣味だな。見るだけで気持がわるくなるものってなに?」
鼓は俊行の前にあるとろろイモの皿を見おろした。かれの本心である。とろろイモにかぎらず、鼓は糸を引く食べ物がすべて気に入らない。
「ヘビが好きでとろろイモがきらい。ふうん。俺と正反対だ。兄貴、変態じゃないの」
鼓はくやしいが言いかえす言葉がない。煙草のひとつもやめられないようでは俊行にからかわれてもしかたがない、と変に弱気になっていた。
「煙草をほんとうにきらいいになって、すぱっとやめるよ。煙草にくむべし、という考えが徹底しているんだ」
「だから階級によってちがうんだよ。禁煙はインテリジェンスの問題だよ兄貴」
俊行はインテリジェンスという語をインテリジェンスと抑揚をつけて発音した。
「インテリジェンス?だから黒人には喫煙者が多いということか」
「またまた‐ネトウヨ差別主義者もマッサオなこと言わないでよ・・兄貴、日本国の総理大臣になれるよ、まったく」俊行はあきれた。「インテリジェンスに黒人も白人もあるわけがないじゃないか。いま階級と言ったばかりでしょ。知識階級の階級だよ。人種は関係ないんだ」
「どう言ったらわかかるのかなあ。つまり煙草は迷信みたいなものなんだ。無知な人間ほど迷信にこだわるじゃない。そのインテリジェンス」
鼓はゆううつになった。煙草ごときで俊行に無知よばわりをされるおぼえはない。かならずやめてやる、と決意をあらたにした。
決意だけが先ばしってあいかわらずからまわりをしているさなかに、部長の山倉が入院した。喉頭癌である。山倉は取りあえず一命はとりとめたものの、手術で声帯をうしなった。癌はすでに体内のどこかに移転している可能性も高いという。彼は回復してももちろん煙草はすえない。それどころか退院後に会社に復帰して仕事をつづけられるかどうかさえあやぶまれる体になってしまった。
喉頭癌のほとんどは喫煙者にとりつく病気である。山倉がそれで倒れたというニュースは、社内の多くの喫煙者をふるえあがらせた。触発されてただちに煙草を断つ社員も出た。
鼓もその機会に乗じて会社で高らかに禁煙宣言をした。ヘビースモーカーの部類に入るかれが、山倉の病気を身につまされて煙草を断つのはふしぎではない、とかんがえる者が社内には多かった。かれはあれほどためらった禁煙宣言を、良心の呵責を知ることなく表明することができた。
鼓は会社で禁煙宣言をした日の晩に典子にも言った。悲壮感を精一杯顔に出したつもりだった。ところが山倉とは面識のない典子は、彼の発癌のニュースを聞いても身につまされる根拠がうすい。
とかるく受け流して澄ましている。まるで鼓が世界一周旅行に連れていってやる、とでも発言したみたいである。彼女の顔には、期待しないで待ちますわ、と言う気持がはっきりと出ていた。
ところがその翌日の晩に鼓が帰宅すると、典子は赤飯を炊いてかれの帰りを待っていた。きのうはそっけないふうをよそおっていたが、鼓の禁煙宣言はやっぱりうれしかったらしい。俊行も呼ばれていていて、娘の香織とともにかれの帰りを待ちわびていた。ご馳走の並んだ夕食がにぎやかにはじまった。
「義兄さん、会社の部長が喉頭癌になったから禁煙したんだって?」
「どうしてって・・…あれは煙草のみがかかる病気だからさ。命はおしい」
「人の病気を見て煙草をやめたということは、自主的に煙草がきらいきらいになった、というわけじゃないんだね。ようするに他力本願なんだ」
奥歯に物がはさまったように言って、俊行はふうんと唇をとがらせている。
鼓はいやな気分がした。かれはきのう会社の休みを利用して、虎ノ門の病院に入院している山倉を見舞った。山倉は首のまわりを包帯でぐるぐる巻きにされて死人のようにベッドに横たわっていた。光のやどらない弱々しい目が包帯よりも無ざんな印象をあたえる。「煙草が好きなら好きなだけおもいきりすいたまえ」と寿司屋で自信たっぷりに鼓に言ったときのかれの姿はどこにもなかった。まるで20も30も年をとったように見える。それだけですめばまだしも、噂どおり癌が体のどこかに移転しているとすれば、かれはすでに死の宣告を受けているのも同然である。鼓は腹の底から煙草はおそろしいとおもった。
彼は病院からもどった直後、煙草を断つ、と営業2課の部下たちにむかって高らかに宣言した。
山倉の癌が身につまされたのが鼓の禁煙宣言の最大の理由であることはまちいがない。が、鼓は同時に、かれを喫煙派の仲間だと勝手にきめつけていた山倉のいないいまが、社内で禁煙宣言をする絶好のチャンスだ、と胸の片すみでかんがえていないこともなかった。他力本願という俊行の言葉は、彼がまるで山倉の病気を待ち望んでいたかのような響きがあって、鼓は屈託した。
「他力でも自力でも煙草をやめることに変りはないだろう。やめることがかんじんだ。方法は関係ないよ」
俊行はまだ意地悪を言う。煙草をやめたい、と鼓が新宿で告白していらい、俊行はとことんかれをからかい続けるつもりでいるらしい。
「無理をしないほうがいいよ義兄さん。無理をして欲望を否定するのは体に良くない。煙草がほしい、煙草がほしい、と正直に言った方が精神衛生上もいいんだ」
「俊行、いい加減にしなさい。あんたまるで煙草をすえ、すえと義兄さんにそそのかしているみたいじゃない。ふざけないで」
「そんなことないよ。義兄さんの禁煙の決意がどれほど強いのかためしているだけさ。これぐらいの誘惑に負けるようなら、どうせ長つづきなんかしない。ね、兄貴」
こんどは兄貴と言い変えて、俊行は鼓の背中をぽんとたたいた。イヒヒと笑う。
「なんとでも言うがいいさ。煙草なんかすこしもすいたいとはおもわないね」
鼓は強がりを言った。食べながら飲んでいるビールがすこしまわってきて、本当は煙草をすいたくなっている。が、その場はたいした努力もしないでやりすごすことができた。
禁煙宣言をしてこの方、彼は会社でも今のようにうまく禁断症状を克服してきている。自分がかかったわけでもない喉頭癌への恐怖心だけではこうはならない。強い緊張感が彼にやすやすと禁断症状を克服させているのである。その緊張感はかれが人目を意識するところから来ている。煙草を断つ、と公言した以上、なにがなんでもそれを口にしてはならない。禁をやぶれば人々になにを言われるかわかったものじゃない、と彼はおおいに気が張っている。
禁煙3日目にもなると、社内では多くの人間が彼の決断のことを知っていた。2課の部下をはじめとする営業部の社員はもちろん、顔見知りの他の部の人々までがかれと会うたびにかならずそのことを話題にしてくれ、はげましてくれる。また社員食堂では食事をしているかれのところにわざわざやって来て「禁煙おめでとう」「ついにやりましたね」「頑張ってください」等と声をかける者もすくなくなかった。まるで大阪支社にでもいるみたいな感じである。
人目は日ごとに多くなった。が、緊張感というものはそう長くはつづかない。禁断症状さえわすれてしまうほどぴんと張り詰めていたかれの気持は、時とともに逆にゆるんできた。それと並行してニコチンへの欲求がだんだん強くなってくる。しかしかれは煙草にはいっさい手を出さなかった。ここが以前とはちがうところだ。緊張感は弱くなったが、かわりにかれ本来の意地っぱりな心根が頭をもたげてきたのである。人目がある限り絶対に煙草はすわない、とかれは意地を張りはじめた。なんのことはない。やはり人目を気にするあまり、ぜったいにに禁煙宣言はしない、とつい3日前までかたくなになっていたときと同じである。煙草に手を出さないのはいいが、意地は張れば張るほど敵の姿も大きくなる。禁断症状はたちまち勢いを盛りかえしてかれを苦しめはじめた。
6日目の昼食後に強烈な禁断症状がかれをおそった。頭のなかの黒い霧がタールのごとくよどんで、左手全体が麻痺したような強いしびれ感がきた。小指どころのさわぎではない。小指の存在さえわからなくなるようなけだるい、腕全体の麻痺感覚である。つづいて頭の内側に例のぎゅっという圧迫感が走る。それもやはりいつもとはちがう。まるで輪ゴムがチェーンに変ったような硬質の強い刺激である。それからの異変はふだんと同じ順序で起きた。が、ひとつひとつの症状の間合いが極端に短かった。そのためかれはすべてが同時におそったように感じた。しかもそれは、体のそこかしこに火がついたような不安感をひき起こして静まる気配がない。
にげるように食堂を離れて、ビルの1階のロビーに出た。受付嬢の目のとどかない角度に置かれている煙草の自動販売機にまっすぐに向かう。コソ泥のようにあたりをはばかって、人が見ていないのをたしかめコインを続けざまに投入口に押し入れた。スイッチを押して煙草が出てくるまでの間がひどく長く感じられる。出てきた煙草をひったくるように取ってポケットにねじ込むやいなや、廊下のつきあたりにあるトイレをめざして小走りにそこを去った。つり銭のことはまったくかれの頭に浮かばなかった。
大便所のひとつに入ってしっかりと鍵をかける。1本だけだ、となんども自分をはげましながら煙草の箱をあけた。火がない!とそこではじめて気づいた。大あわてでそこかしこのポケットをさぐる。さいわい背広の胸ポケットの底に赤坂のバーのマッチがのこっていた。それはかれが一昨日係長の吉川とともに取引先の接待を受けた時の店のマッチである。隣にすわった女が帰りぎわにかれのポケットに忍び入れたのを、鼓はすっかりわすれてそのままにしていたのである。
ふるえる手で火をつけて一服すう。立ちくらむほどの衝撃があった。やりすごして再びニコチンを取りこむ。めまいが頭から全身にひろがるような奇妙な充足感がある。マリファナでもすうように唇をすぼめて、彼はさらに深々と煙を肺に送った。
遠くの早鐘のように心臓がこきざみにふるえているとおもった。とたんに頭のなかが凛とさえて、五体が溶けてからみ合うめまいのような甘い感覚が消える。体の各部がシャキとそれぞれの位置におさまって、全身に力がみなぎった。
それがはじまりだった。人目をしのんで煙草をすうのが鼓の習慣になった。
煙草はいまでは以前とはくらべものにならないくらいに素敵な味がする。
(了)
official site:なかそね則のイタリア通信